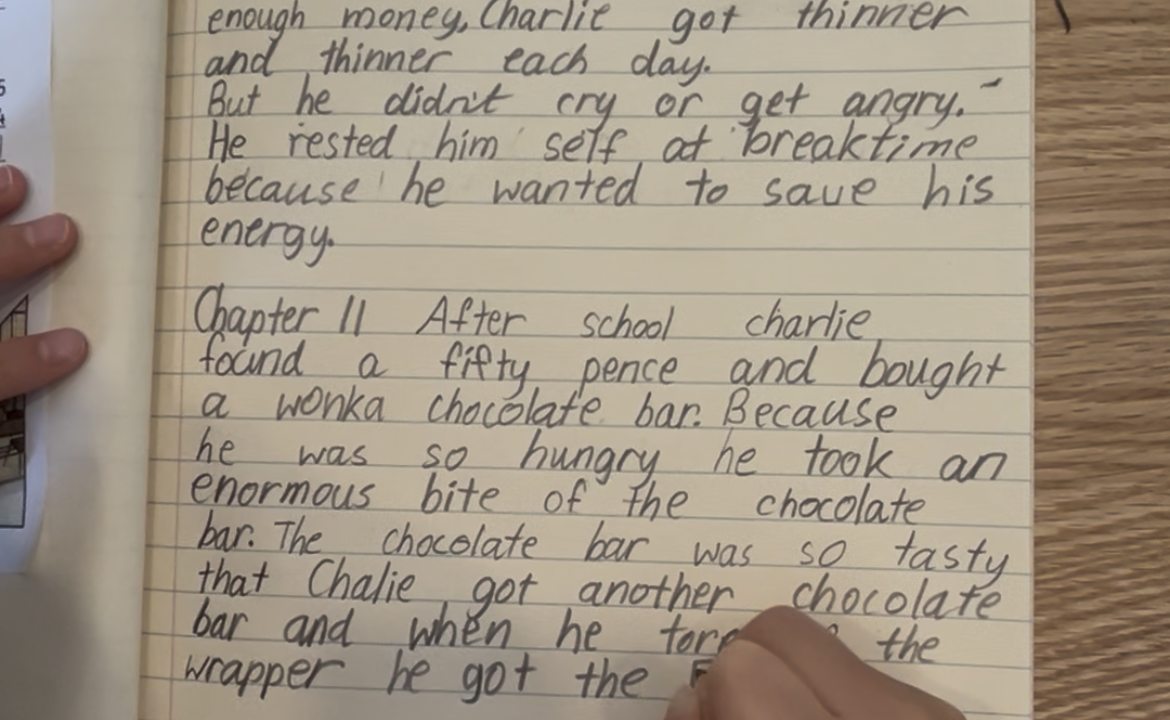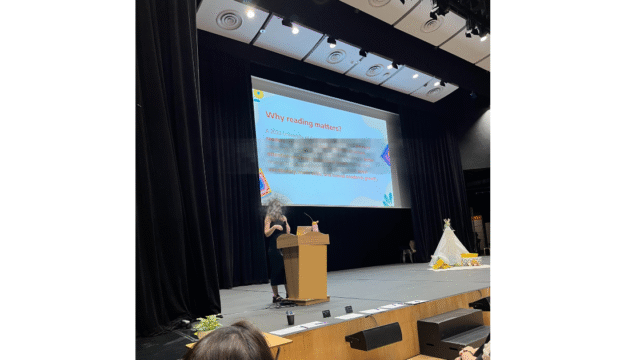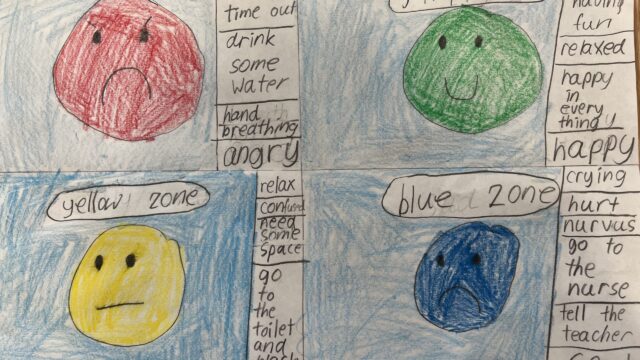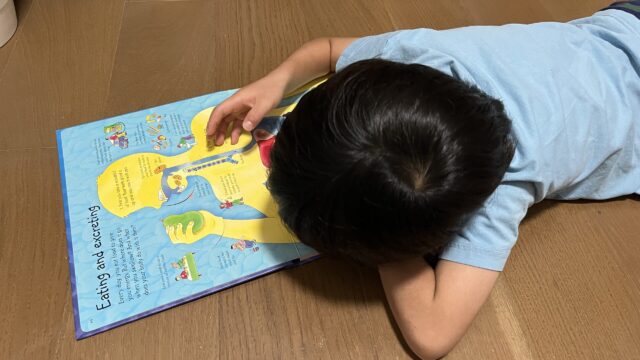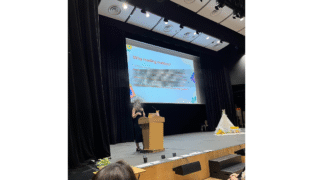海外のインターナショナルスクールに通うと、
「宿題が思ったよりすごい…!」と驚くママ、多いですよね。
私もシンガポールで子どもを通わせていますが、
どんな宿題を持って帰ってくるか、毎回ドキドキ。
教科書もないし、宿題の内容も予測不能!
でも今ならわかります。
この宿題こそ、インターが子どもに育てたい力のすべてなんです。
🌏 インターの宿題は“創造力トレーニング”
インターナショナルスクールの宿題には「教科書」がありません。
カリキュラムはあるものの、毎日の宿題はとにかく自由度MAX。
だから、親は「今日なに習ったの?」と毎日スリリング。
でもそれがインター流の教育。
「正解を出す力」よりも、「考えて表現する力」を育てる宿題なんです。
🍫 娘の宿題がカオス(でもすごい)
小学低学年の娘が、授業で『チャーリーとチョコレート工場』を
読んでいるときに出された宿題がこちら👇
-
「自分だけのオリジナルスイーツを発明して!絵も描いてね」
-
「登場した女の子の性格を、授業中習った形容詞を使って説明しよう」
-
「この章を要約してみよう」
……え、要約って。小学生だよね?😳
でも、これが普通なんです。
読解力・語彙力・表現力・創造力、ぜんぶを使う“総合宿題”。
日本の穴埋め式ワークとはまるで違って、
「自分の考えを英語で言葉にする練習」そのものが宿題なんです。
💡 なぜインターの宿題はこんなに難しいの?
① テキストがない=「見えない不安」
授業内容がわからないから、親は不安。
でもそれがインター流。
子どもが“自分で考えて答えを見つける”仕組みなんです。
② 答えがひとつじゃない
「どう思う?」「なぜそう考えた?」がメイン。
つまり、“思考力の筋トレ”。
間違いなんて存在しません。
③ 先生がとにかく褒め上手
間違えても全力で褒めてくれる。
「努力したこと」が評価されるから、子どもも自信をもてるんです。
🧠 宿題を自力でこなせるようになる3つの力
1️⃣ 「話す力」
宿題ができる子は、授業で聞いたことを話せる子。
まずは、家で話す習慣をつくること。
🗣️今日からできるママの魔法の質問:
-
「今日はどんなことを習ったの?」
-
「一番おもしろかったのは?」
-
「その時、どう思った?」
子どもが「ママに話したい!」と思うようになると、
授業への集中力もぐんと上がります。
2️⃣ 「間違えてもOKの勇気」
インターでは、“間違える=悪い”じゃない。
“挑戦した”ことが評価されます。
我が家では、
「完璧じゃなくていい、まず書いてみよう!」が合言葉。
ママが答えを言いすぎると、“ママの宿題”になっちゃう💦
なので、手を出しすぎず、見守る勇気を。
先生たちはプロ。
全力で褒めて、モチベーションを上げてくれます✨
3️⃣ 「読む力」
宿題の多くは読書に関連しています。
読書が好きな子は、宿題への抵抗が激減!
でも、読書嫌いな子に「読みなさい!」は逆効果。
本を楽しむ環境を作ることが大切です。
🕯️我が家の読書ルール:
-
寝る前の15分は「リラックス読書」
-
ママも一緒に読む(同じ空気感で)
-
「どんな話だった?」を共有する
読書習慣がつくと、宿題の理解力も一気に伸びます📈
👉 詳しくは別記事でまとめています:子どもの読書習慣をつけるコツ
💬 我が家のリアル
長女(小学校低学年)は
「今日ね〜」と楽しそうに話してくれるタイプ。
でも弟(園児)は、
「何もしてない」で終了(笑)。
そんな時はあきらめず、
「体育では何した?」「お友達が言ってたこと、面白かったね」など、
話しやすい話題から引き出すと、意外とポロッと出てくることも。
話す=思い出す=記憶が定着する。
だからこそ、ママが聞いてあげる時間が一番の学習サポートです💬✨
🌈 まとめ:インターの宿題は“自立の第一歩”
| 日本の宿題 | インターの宿題 |
|---|---|
| 正解を出す練習 | 自分で考える練習 |
| 教科書通り | 自由で創造的 |
| ママがチェック | 先生がほめて伸ばす |
最初は「これ無理!」と思っていた宿題も、
今では娘の成長を感じる最高のツール。
『チャーリーとチョコレート工場』の授業をきっかけに、
「学ぶって楽しい!」と感じるようになったのは、
まさにこの“考える宿題”のおかげです。
💬 私も日々、英語教育と日本語教育のバランスに悩みながら奮闘中のママ。
でも、どうせ大変なら——一緒に楽しんじゃいましょう。
今日も「宿題タイム」を、親子の成長タイムに✨
📖 関連記事